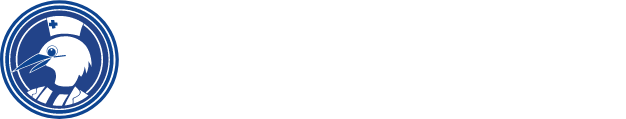医療法人社団福寿会
 03-3880-1221
03-3880-1221
リハビリテーション
また、外来通院でのリハビリテーションも行っています。
主に脳血管障害(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など)、難病(パーキンソン病、脊髄小脳変性症等の変性疾患等)、外傷(骨折、腱・靭帯断裂またその手術後)、慢性の関節疾患(リウマチ、変形性股・膝関節症等)、人工関節置換術後、外科の手術後や肺炎後などの廃用症候群、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの患者様を対象に行っています。

施設基準
- 脳血管疾患等リハビリテーション ( II )
- 廃用症候群リハビリテーション ( II )
- 運動器リハビリテーション ( I )
- 呼吸器リハビリテーション ( I )
- がんリハビリテーション
運動療法

筋力やバランス、体力などの改善を目的に運動を行います。
動作訓練

「起き上がる」「立ち上がる」「歩く」などの目的に運動を行います。
動作の改善や、「食べる」「着替え」「トイレ」など日常生活に欠かせない動作の獲得を目指します。
レッドコード

当院ではリハビリテーション科に「レッド・コード」を導入しています。整形外科医師の診断により、療法士と1対1でのレッド・コードを用いた治療を受けることができますので、痛みや体の硬さで日常生活に不便を感じている方は、ぜひ、レッド・コードでのリハビリを受けてみてください。
物理療法

痛みの緩和、リラクセーション、循環の改善を目的として、温熱や電気、牽引療法を行います。
- レッドコードとは
-
リハビリテーションの手技の中に、100年以上前に発明された、スリング・エクササイズというものがあります。主に腰痛患者に対して行われていました。腰痛は自分の身体の重さが原因と考え、天井から降ろしたロープで体の一部を吊り下げることで、腰にかかる負担を減らし、痛みを無くそうというものでした。ただし、スリング・エクササイズの道具は特殊で、基本的な使用方法もまちまちであったため、一般に広まることはありませんでした。レッド・コードはそれを一歩進め、扱いを簡単にすると共に、ロープで体の一部を吊り下げながら運動することで、体にかかる負担を減らすだけでなく、筋肉の力を付ける事もできます。腕や足の重さをロープで支えることで、普段は使っていない筋肉や、関節の動きを引き出すことができます。
レッド・コードはこんな人にお勧めです
- 関節に痛みがある人
- マッサージ等を受けているがあまり痛みに変化がなく、運動の苦手な人
- とにかく体が硬く感じていて、時には痛みを感じる人
当院では、ノルウェイ製リハビリテーション機器、レッド・コードを導入しています。
レッド・コードには様々な使用法があるのですが、2例紹介させて頂きます。1. 片脚立位用
まず、一つ目は「上肢で支えることなく、部分免荷の下肢整形疾患患者に片脚立位の練習が出来ないか?」という疑問から思いつきました。
一般的な方法では、平行棒内において、患者は両上肢で自分の体重を支え、患肢足部に体重計を置いて荷重量を調整しながら行います。しかしながらこの方法では、患者は上肢の筋出力調整に注意を多く割かれてしまい、下肢の荷重感覚、筋感覚調整は難易度が高いと考えていました。そこで思い出したのが子供の時によくやったブランコです。
ブランコをこぎ出す前に臀部にブランコの台をあてて、後方に下がります。この時、下肢にかかる荷重は身体の重心と足部の地面との接触点を結んだ線と、垂直線のなす角度によって変化します。角度が 60°なら体重の 2/3、45°なら 1/2 といった具合です。いわゆる三角関数です。もちろん、実際には足部に体重計を置いて確認してから行いますが、訓練中は外しています。これによって、足部と身体重心の角度に大きな変化が無ければ、片脚で身体を支持しても部分免荷は保持できます。また、膝関節の屈伸運動をすることで、下肢の運動と体幹の運動を連動させる練習もできます。つまり、支持なし独歩の練習にもなるわけです。しかしながら、この練習方法には大きな誤りがありました。
レッド・コードで骨盤を保持している為に、運動時に股関節の参加が制限されている事です。これでは「部分免荷での片脚立位練習」というには不十分です。
現在では、レッドコードで骨盤上部から腰部にかけてを保持するようにしています。この方法では適応患者が減ってしまいましたが、単なる片脚立位だけでなく、股関節-膝関節足関節の運動連鎖の練習にもなりました。
2. 立位バランス練習用
こちらの練習は、球技スポーツを趣味としている下肢整形疾患の患者の治療に用いたものです。
残念ながら、私は球技スポーツが苦手でリハビリの道具として使用する以外はボールを持ったことはもう30 年近くありません。しかしながら身体運動の専門家という自負はありますので、患者の「もう一度球技をやりたい」という希望に添えるよう、なんとかしなければなりませんでした。
球技においては、空中で体幹を大きく回旋し、その状態でボールコントロールをしなければならないという運動条件がありました。当然、空中にとどまったまま筋力強化練習をすることはできません。そこで、運動条件の中で必要な要素を取り出し事にしました。
この練習では、出来るだけ不安定な環境で、上部体幹と下部体幹が逆方向の運動を行う様にしています。レッド・コードにボードを取り付け、ボードの下にはボールを置きます。ボードは前後と側方、そして傾きにおいて不安定です。
また、ボールは転がり抵抗を生みますので不安定の度合いはボールを使わなかった場合と比べて穏やかになります。
患者はボードの上に立ち、やや腰を落とします。まっすぐ立つのに比べて、膝・股関節の役割が増すので難易度が上がります。そして、一方を固定したゴムチューブを両手で把持し、上肢の運動ではなく、体幹の回旋によりゴムチューブを引っ張ります。上部体幹はゴムチューブを引っ張る方向に動きますが、下部体幹はその反力により、反対方向に動きます。患者は体幹回旋を軸ではなく、点として調整しながらバランスを取り続けなければなりません。
実際に行ったのはこの訓練だけではありませんでしたが、患者さんからは「(怪我の)前より動きやすいかもしれない」と言われたので、ほっと胸をなでおろしました。